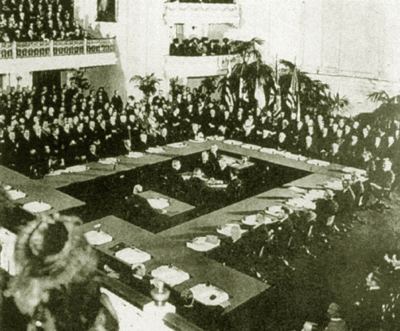
大川周明先生のラジオ講義の、今日は5日目です。
(「米英東亜侵略史」は、先生のラジオでの講義を録取したものです)
なお、文中にある(注)は、ねずきちによる挿入です。
≪初日≫黒船来航
≪二日目≫米国東亜政策変遷
≪三日目≫米国の太平洋進出
≪四日目≫無鉄砲な米国外交
≪五日目≫米国の横車
===========
東亜において遮二無二日本の地位を覆えそうと焦り、国内では没義道な日本人排斥を強行した米国は、さらに強大な軍艦の建造に着手します。
米国における大海軍論の偉大な先駆者は、「歴史に於ける海上権の影響」といふ名高い本を著わしたマハン海軍大佐です。
これを実行に移したのが、セオドラ・ルーズベルトです。
明治31(1898)年3月、当時海軍長官だったルーズベルトは、この本を読んだ感激を著者のマハン大佐に書き送っています。
その手紙には、こうある。
~~~~~~~~~~
貴下の著書は、私の心中に漠然と存在していた思想に、明確なる姿を与えてくれました。
私は崇高なる目的のために貴著を研究しています。
~~~~~~~~~~~
そしてルーズベルトが後年大統領に就任したときに述べた言葉です。
~~~~~~~~~~~
第一等の海軍建設を議会に要請することは、大統領たる私の荘厳なる責任である。
~~~~~~~~~~~
ルーズベルトは、大統領就任時に、強大な海軍なくしては、米国はChinaの門戸開放主義を有効に維持しないし、モンロー主義も守り得ないと力説し、敵海軍主力の撃滅を第一目的とする大戦艦隊建造の必要を強調したのです。
注)モンロー主義=ヨーロッパ諸国の紛争に米国は関与しないとした主義思想。
大東亜戦争に至る米国海軍政策は、このルーズベルトの精神を継承し、かつこれを実行したものです。
米国の海軍記念日は10月27日ですが、これはルーズベルトの誕生日でもあります。これは決して偶然ではないのです。
こうして米国海軍は、ルーズベルトの指導の下に強大な基礎を置き、さらに大正3(1914)年8月14日には、太平洋と大西洋とを結ぶ、パナマ運河の開通を見ています。
この運河の開通によって、以前ば大西洋岸ハムプトン・ローズ軍港からカリフォルニアのメーア軍港に到るために、南米大陸を迂回して実に13000海里の航海を必要としたものが、わずか5000海里の距離に短縮されました。
米国海軍は、その全力を挙げて、大西洋、太平洋、両方の作戦を実行し得るようになったのです。
このことは、米国はその艦隊を倍増させたのと同一の効果を生んだことになります。
加えて大正5(1916)年には、ダニエル海軍計画、イルソン海軍法として知られる海軍の大拡張計画が着々と実行されるようになった。
次いで大正8(1919)年には、いよいよ太平洋艦隊が編制され、太平洋における米国の勢力は、にわかに強大なものとなったのです。
そのダニエル海軍計画というのは、戦艦10隻、巡洋艦6隻を基幹とし、なんと120隻近い駆逐艦及び潜水艦を建造するというもので、計画の翌年(大正6)には、ただちに建艦の実行に着手しています。
この計画は、世界の海軍国を誇る英国をひどく刺戟したのだけれど、米国は国内の反対圧力に対して、東亜問題に於ける日米の衝突を力説することで、大建艦計画への反対圧力を屈服させています。
このダニエル海軍計画が米国議会を通過した大正6(1917)年、日本は、八四艦隊計画をたて、翌年には八六艦隊計画、その翌々年には八八艦隊計画をたてています。
このあたりの状況は、英国の海軍通であるバイウォーターが著書の「海軍と国家」に詳しく述べています。
引用します。
~~~~~~~~~~~
日本は一年以上にわたって、海上の覇権を握ろうとする断乎たる目的で行われた米海軍の大規模拡張を、不安の念を高めっつ眺めていました。
日本の利害は太平洋の守備にあります。
米国は、その太平洋に、海軍力を集中させたのです。
大正8(1919)年8月、米国海軍の最強艦隊が、新たに編制された太平洋艦隊として、パナマ運河を通って太平洋にやってきます。
同時に太平洋艦隊根拠地の計画が発表された。
そこに書かれているのは、まさにフィリビン、グアム、サモアにおける大規模な海軍施設の設置であり、ハワイの真珠港の強化です。
ここまでくると、さしもの日本も、米国の海軍行動は、日本を敵国としたものと気付かざるを得ません。
かくして日本は大正9(1920)年、名高い八八艦隊計画を立てるに至ります。
~~~~~~~~~~
こうして、日露、第一次世界大戦後の世界は、米国の大建艦の実行に伴い、いやおうなく猛烈な建艦競争に巻き込まれていきます。
そして日本の造船工業は、少ない予算の中で全力を挙げて奮闘し、船台・船渠・港湾の設備から見て、あるいは造船技術上から見て、性能面で米国を凌駕する艦隊を構築します。
つまり、金力だけは米国に劣るけれど、その他の点では、明白に日本勝利の自負を固めていったのです。
加えて米国の海軍計画は、ひとり日本だけでなく、同時に英国の海軍拡張をも促します。
米国がいかに豊かな国であるといっても、日英両国を相手にしての建艦競争は、これは無謀というものです。
その上世界大戦による米国の好景気も、いつまで続くものではない。
米国が一朝、経済的不況に陥れば、莫大な経費を海軍に奪われることは、財政面で大きな苦痛となる。
かくして米国は、自分で巻いた種からの苦境から脱出すべく、海軍軍縮会議の開催を呼びかけたのです。
この軍縮会議によって、日英両国の海軍の建艦に足かせをはめると同時に、東亜に於ける日本の勢力を失墜させ、もって太平洋進出の路を平坦にしようともくろんだのです。
こうして、大正10(1921)年、同11(1922)年のワシントン軍縮会議が開催されます。
ワシントン軍縮会議は、ロンドン・タイムスの主筆のスティードが喝破した通り、その本質はまさしく「日米両国の政治的決闘」だったのです。
この決闘で米国は、先づ第一に、米国にとって最も都合の悪い日英同盟を破棄させ、日本を国際的に孤立させることに成功します。
そして第二に、日本海軍の主力艦を自国ならびに英国のそれに対し、6割に制限させることに成功しています。
このとき日本の加藤全権は、英米海軍主力艦に対する七割のそれを以て、日本国防の最小限度なりとし、極力米国案に反対したにもかかわらず、英米両国の共同作戦によって、遂に太平洋西部の防備制限を交換条件として、国防の「最小限度」以下の比率を承諾したのみならず、加藤全権は次のような驚くべき声明までもしています。
~~~~~~~~~~~
日本は過去にも未来においても、その海軍力を合衆国や英国と同等にする意思をもっていない。
~~~~~~~~~~~
加藤全権のこの声明は、すこぶる英米人の拍手喝采を博しています。
日本を孤立させ、その海軍力を明らかな劣勢に導いた米国は、さらに四ヵ国条約の締結によつて、西太平洋に於ける自国領土の安全を図ります。
この条約は、もともと米国の筋書きでは、日英米三国の間で条約締結し、その成立と同時に日本にとっての生命線である日英同盟を破棄させてしまおうというものです。
途中でフランスのメンツもたてなきゃならないということになって、四ヵ国条約となった。
ここで問題なのが、西太平洋に於てフランスよりはるかに大きな利権を持っているオランダです。
そのオランダが、米国主導のこの太平洋条約の当事者国としてはいっていない。
この点からも、要するにこの条約の意図や見え見えということになります。
条約の要約の要旨は、その第一条に尽されています。
~~~~~~~~~
第一条 締約国は、太平洋方面に於けるその島嶼たる属地及び領地に関する各自の権利を、互に尊重すべきことを約す。
もし締約国の何れかの国に、太平洋問題に起因し、かつ前記の権利に関する争議を生じ、外交手段によつて満足なる解決を得ることができず、かつその間に現存する円満なる協調に影響を及ぼすところある場合には、右締約国は他の締約国の共同会議を求め、当該事件全部を考量調整のため、その議に附すべし。
~~~~~~~~~
そしてこの条約の第四条では、
~~~~~~~~~
明治44(1911)年7月13日、ロンドンに於て締結せられたる大ブリテン国及び日本国間の条約は、これと同時に終了するものとす。
~~~~~~~~~
これで、日英同盟には、最後の引導がわたされたのです。
日本はワシントン会議に於て、山東問題に関してはベルサイユ条約によって得た権利をさへも犠牲にし、ほとんど無条件にこれをChinaに返還しました。
石井・ランシング協定の廃棄にも同意しました。
Chinaに関する九ヵ国条約が、米・白・英・仏・伊・日・蘭・葡・支の九ヵ国間に、実に米国の思惑通りの内容で成立するのを認めています。
この条約では、
~~~~~~~~~~
Chinaの全領土にわたって、一切の国民の商業及び工業に対する機会均等主義を有効に樹立維持するために努力する。
友好国の臣民または人民の権利を減殺すべき特殊権利、または特権を獲得するために、Chinaの情勢を利用しない。
締約国は、本条約の規定の適用問題に関係し、かつ右適用に関して討議することが適当であると認める事態が発生した時は、何時にても右目的のため、関係締約国間に十分かつ隔意なき交渉をなすべきこと。
~~~~~~~~~~
と決められています。
要するに米国は、この条約によって、少くも形式的には、我国のChina、特に満蒙に於ける特殊権益を剥奪し去ったのです。
かくしてワシントン軍縮会議は、太平洋に於ける日本の力を劣勢にすること、東亜に於ける日本の行動を拘束することにおいて、米国をしてその対東洋外交史上、未曾有の成功を収めさせたのです。
米国が東洋に向って試みた幾度かの猪突猛進はその都度失敗に終ったけれど、ワシントン軍縮会議において、ようやくその横車の目的を遂げたのです。
けれど米国は、これだけでは満足しなかった。
ワシントン会議で日本の戦闘艦の制限はできたけれど、それだけではまだ枕を高くして眠れない。
米国と日木のように、遠来の距離を隔てて相対している間柄では、大きい巡洋艦が時として戦闘艦以上の効力を発揮することがあります。
かくて米国は、自国を主動国として、今度は主力艦以外の軍艦制限の目的をもって、ジュネーブ会議、ロンドン軍縮会議を提唱します。
こうして日本は、ワシントン軍縮会議だけでなく、これら会議でも米国に屈服してしまいます。
ちなみに米国に屈服したのは日本だけではありません。
実に英国まで、米国の前に頭を下げ、「軍縮」の美名のもとに、米国よりも劣勢なる海軍を以て甘んずることになったのです。
それまで世界第一の海軍を国家の神聖な誇りとしてきた大英帝国が、その国力の発意である海軍力の王座を米国に譲ったのです。
このことは、世界史における大事件といわなければなりません。
ここで、私たちは、もう一度心静かに、米国の国際的行動を振り返ってみたいと思います。
自ら国際連盟首唱しながら、それが成立すると、これに加わることをしない。
不戦条約を締結し、戦争を国策遂行の道具に用いないと他の列強に約束させておきながら、東洋に対する攻撃的作戦を目的とする世界第一の海軍を保有する。
大西洋において英米海軍の比率は、10:10なのだから、なんら平和を脅かすことはしないと称しながら、太平洋に於ては日米海軍の7対10の比率でさえ、なお平和を脅びやかすものであると力説する。
ラテンアメリカ諸国に対しては、門戸閉鎖主義を固執しながら、東亜に対しては門戸開放主義を強要する。
これは例えば、日本人漁業者が、メキシコのマグダレナ湾頭に土地を借りようとしたとき、米国のモンロー主義に反するから認められないという決議が米国上院を通過している。
しかるに米国は、東亜において日本が占めている地位は、米国がメキシコやニカラグアに占める勢力の十分の一にも満たないにも関わらず、門戸開放主義の名において、これを否定し、日本の権益を有名無実化しようとする。
要するにこれらの米国の行動は、まったくの無反省で、しかもあくなき利己主義からくる矛盾の行動です。
米国の乱暴狼藉は、あまりにも無茶苦茶であるにも関わらず、当時、世界のどの国も、米国に向って堂々とその無理無法、横車を糾弾する者はなかった。
日本も、ロンドン会議の席上で、補助艦比率で堂々と10:10を主張すればいいものを、ワシントン会議以後の情勢変化、および不戦条約の精神を楯として、主力艦6対10の比率だって変更要求できたであろうにもかかわらず、あたまから7:10の比率に甘んじ、しかもその主張さえ米国に拒否され、一層の劣勢を以て甘んじたのです。
これらの会議は、簡単に「軍縮会議」と呼ばれているけれど、大事なことは、これらの会議は単純な海軍会議ではないということです。
30年にわたる執拗極まりない米国の東亜政策全体を顧みることによって、はじめてこれら会議の真意を、正しく理解できる。
私は、意気揚々とロンドン会議を引上げた米国代表のスティムソンが、この年の5月13日に、上院外交委員会において次の説明を行い、口を極めて日本代表及び日本政府を称賛したことを忘れることが出来ません。
~~~~~~~~~~
我等合衆国代表が眼目としたのは、米国海軍が日本海軍を凌駕すべき製艦計画を完成するまで8年間、日本をして現勢力のままにあらしめることでした。
我々は日本に対し、米国艦隊の保有艦船数が75000トンに拡張するまで、日本は海軍力を増大させないようにと要求しました。
米国はこの条約によって、巡洋艦を倍増させることができることになったにもかかわらず、日本は現在保有する98000トンより、わずかに2000トンを拡張し得るに過ぎないのです。
日本政府は、国内において海軍拡張論者の猛烈な運動にあい、また海軍当局ぽ国民の圧倒的な支持後援を得ていました。
ですから私は、日本代表はロンドン会議に於て非常に困難なる仕事を成し遂げたと断言いたします。
我等は、日本が勇敢にも、その敵が自国を凌駕するまで、その手を縛るがごとき条約を承認したことに対し、その代表及び政府に最大の敬意を払ひつつ、会議から引上げて来ました。
我等は故意に潜水艦を日本と同等にしました。
これは、潜水艦の総トン数を縮小すれば、それだけ我国を有利に導くからです。
かくして日本は、16000トンの縮小に同意したのです。
~~~~~~~~~~
ロンドン会義に於ける日本代表及び日本政府は、アノリカ代表から、「敵が自分よりも優勢な艦隊を建造するまで、自分の手を縛るような条約に調印した」と言って、その「勇敢」を賞めそやされたのです。
その日本代表は、ロンドンから帰ると、日本国民に向って会議の成功を語り、首相は議会において、
「国防の安全を保証して居たのであります」と述べた。
痛憤に堪えなかった私は、我等の機関紙であった月刊「日本」のこの年の5月号に、「ロンドン会議の意議」と題する一文を発表し、その末尾を次のように結んでいます。
~~~~~~~~~~
ロンドン会議は、もしそれが単独に海軍協定のためのものであるならば、多少の譲歩は、これを良しとします。
しかし、これまでの四半世紀にわたる米国の東洋政策遂行の歴史を観、そのうえでこの会議を観たとき、既にワシントンで譲り、いままたロンドンで譲るならば、やがて一層大なる譲歩を強要させられるに違いないこと、火を見るよりも明らかです。
繰返して述べた通り、米国が志しているのは、いかなる手段を以てしても太平洋の覇権を握り、絶対的に優越する地位を東亜に確立する、ということです。
そのために米国は、日本の海軍を劣勢ならしめ、無力ならしめ、しかる後にChina満蒙より日本を駆逐しようというのです。
これに対して、日本は、ほぼ何も抵抗しなかった。
そのため、米国の日本に対する傍若無人は、年と共に激甚を加えてきたのです。
このままいけば、日本が米国の属国となり果てるか、さもなくば国運を賭して戦うかの選択を迫られることになる。
日本は、たとえばロンドン会議の席上において、日本の覚悟を知らしめ、断固米国に抗議するべきであったのかもしれません。
しかし日本は口頭の抗議さえもせず、ついに抗議する機会さえも逸してしまったのです。
≪大川周明先生「米英東亜侵略史」(6)に続く≫
~~~~~~~~~~~~
(ねずきちより)
ワシントン軍縮会議は、戦艦保有率を日:米:英、3:5:5にするというものでした。
当時の日本は、日露戦争に要した莫大な戦費による財政赤字が国庫の財務を圧迫していたのだけれど、国際紛争は、そうした日本の台所事情などおかまいなしです。
当時の日本政府は、米国の軍縮の提案が、当年度会計予算を軽減できる絶好のチャンスだったと踏んだわけです。
ところがこれは会社の経営でいえば、新たな機械を入れれば(軍艦の建造をすれば)生産量の格段の向上と製品の低価格化が実現できる(国力を増し日本があなどれない国として世界の中での発言権と自国の安全を確保できる)というビッグチャンスに、今期決算が厳しいと経理(国会)からケチがついたために、機械の導入をあきらめた。
その結果、ライバル会社に売上でも収益でも水を開けられ、結果会社が倒産するに至ってしまった。
企業でも国家でも家庭でも、少々金がかかっても、やらなければならないときはやらなければならない、ということなのだろうと思う。
そしてもうひとつ、ワシントン軍縮会議の行われた大正10(1921)年というのは、米国の南北戦争が終わってから、ちょうど59年目にあたる年です。
アメリカ合衆国の建国は1776年7月4日だけれど、実際に米国がいまの姿になったのは、南北戦争が終わり、アメリカ合衆国とアメリカ共和国が統合されてからのことです。
その意味では、南北戦争の終わりが、米国の実質的建国といっていいかもしれない。
そして新たに建国された米国は、まさに新興国家として既存の欧米諸国が持っていた世界の植民地の既得権を、自国でも欲しがるようになる。
そしてまだヨーロッパ列強諸国に植民地化されていなかった空白地帯が、大川先生のいう「東亜」すなわち、Chinaや満州などであったわけです。
米国は、ありとあらゆる手段を講じて、これを積極果敢に奪いにかかる。
建国59年目といえば、中華人民共和国の建国が1949年です。
中共は、建国から今年で62年目なのだけれど、こうした歴史が浅くて若い新興国で、かつ大国というのは、ある意味、欲望むき出しになる傾向があるのかもしれない。
その意味で、米国と日本の戦前の時代考証は、現代の中共と日本の関係に置き換えて学ぶことのできる事柄なのではないかと思います。
横車を押して押して押しまくる。
その横車が通らないとなると、こんどは上手に建前論を振りかざして、自国の都合のいい方向に日本を振り回す。
まるで同じといえるのではないでしょうか。
大川先生が言われる通り、日本はさしたる抵抗もせず、米国の謀略に易々とひっかっかってしまったがために、結果、最後は戦争という、しかも乾坤一擲の大勝負に出ざるを得なくなった。
国際関係においては、日頃から徹底して毅然とした態度をとり続ける。何があっても自国を守り抜くという決意と絶え間のない行動が大事であることを、過去の歴史は教えてくれているように思います。
ちなみに、こうしたいわゆる「軍縮会議」が、結果として大東亜戦争の引き金となっていったという件に関しては、当ブログの「航空戦艦伊勢と日向の物語」にも、詳しく書いています。
お時間のある方は、是非、ご一読されるといいかと思います。
↓クリックを↓



